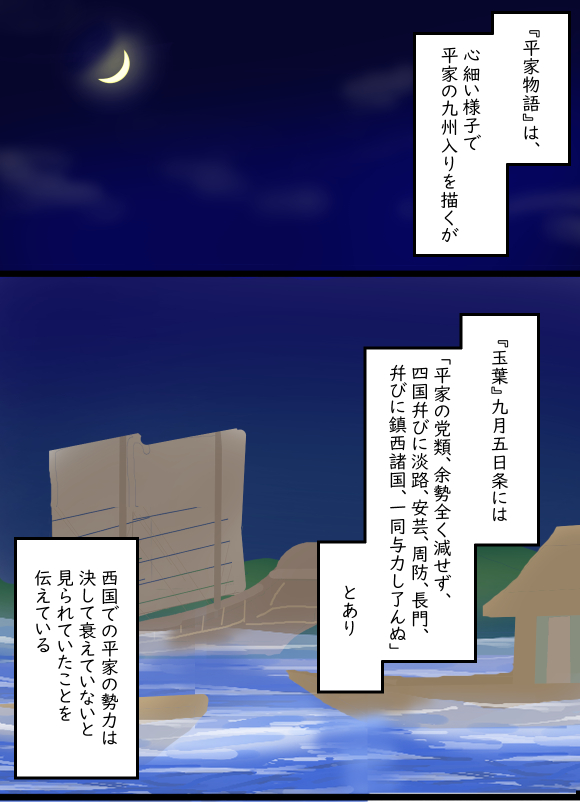大宰府、月夜の歌会!【平維盛まんが21】 平行盛と平家の歌人たち 『平家物語』
大宰府で見上げる、九月十三夜の月。都を思い出し、平家の歌人たちは歌を詠む…。
今回は和歌のお話(^^)
<『平家物語』巻八より>
※漫画はえこぶんこが脚色しています。
登場人物
平資盛 たいらのすけもり
平清盛の長男[重盛]の次男。維盛の弟。
平行盛 たいらのゆきもり
平清盛の次男[基盛(=重盛の同母弟)]の長男。維盛・資盛のいとこ。
平家、大宰府に入る
寿永2年8月26日、平家は九州に入り、
大宰権少弐・原田種直の宿所を、天皇の御在所としました。
原田種直は、清盛・頼盛の元で、平家の鎮西支配、日宋貿易を支えてきた人物です。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『平家物語』では、平家一行は宇佐八幡宮にも参詣していて、そこで宗盛が夢の中で、神に見限られる不吉な託宣を聞く、という場面があります。
九州に着いた矢先に、平家の先行きを曇らせるような不穏な演出です。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『平家物語』は、平家の九州入りを心細げな様子で描くのですが、
同じ頃の『玉葉』寿永2年9月5日条では、
とあり、
都では、西国における平家の勢いは衰えていないという見方がされていたことがわかります。
月夜の歌会
『平家物語』には、大宰府にて十三夜の月を眺めながら、平家の歌人たちが歌を詠む美しい場面があります。
※この場面も諸本によって異同が多く、行盛の歌は、屋代本・南都本・源平盛衰記などにはあるももの、覚一本にはありません。(本によっては歌が違います。)
※歌会が行われた時と場所を、大宰府落ち後の柳ヶ浦とする本もあります。(延慶本・屋代本など)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『平家物語』には、和歌がたくさん載っていますが、必ずしも平家の公達ご本人が詠んだ歌というわけでありません。
平家物語の作者が、登場人物になりきって創作した歌の場合もあるからです。
この大宰府の歌会で、本人作だと確認できる和歌は、平経正の
です。
この歌は、『月詣和歌集』巻九に「平経正朝臣」の名で入集しています。
『月詣和歌集』とは、寿永元年、賀茂別雷神社の神主である賀茂重保が編纂した私選和歌集。
歌人として名高い忠盛・経盛・経正・忠度はもちろん、同じく歌詠みとして知られる資盛・行盛、また、通盛・重衡・業盛などの平家の公達の歌も多く所収されている有難い歌集です。
「わけてこし…」の歌ですが、
「わけてこし…」の歌ですが、
寿永元年(1182)に編纂された和歌集に既に載っているということは、これは経正が都落ちする以前の作ということになります。
実際には大宰府で詠んだ歌ではないのですが、内容がこの場面に、うまいこと収まったんですね。『平家物語』作者のファインプレーです。
※『忠度集』『経正集』『月詣和歌集』については、こちらの記事でくわしく解説しています。
平行盛
維盛・資盛のいとこ、平行盛が登場しました。
平行盛の父は、平基盛(平重盛の同母弟)。
父・基盛が23歳で早世した為、行盛には父親の後ろ盾がなかったので、維盛たちに比較すると昇進はゆるやかですが、
(正五位下。左馬頭、播磨守兼任)
基盛と重盛が同母であったことから、行盛はいとこの小松家兄弟とは親しい間柄だったのではないかな~という想像ができます。
覚一本『平家物語』では、壇ノ浦まで生き残った小松家兄弟(資盛・有盛)と行盛が、三人で手を取り合って入水しています。
※平家の公達の最期には諸説あります。
資盛と有盛が二人で入水したとする本(『長門本』)、資盛が自刃したとする本(『延慶本』『四部合戦状本』)、また資盛は豊後で既に投降していた(『玉葉』)、豊後で討たれた(『源平盛衰記』)、壇ノ浦にはいなかった(『醍醐雑事記』)という説もあります。
行盛と藤原定家
傍流の宿命として、行盛は、わりと何度も戦場の前線に派遣されているのですが、
(近江の戦い、倶利伽羅峠の戦い、京都防衛戦、藤戸の戦い等)
彼は武将というよりも、歌人として名を残した人です。
行盛は、幼少の頃から和歌を藤原定家に師事していました。
「延慶本」「長門本」等の読み本系『平家物語』には、藤原定家と行盛師弟の、心あたたまるエピソードがあります。
定家さま……。最高かよ……。
(T△T)
定家は、平行盛にも神対応をされていますね。
歌人が和歌に込めた思い、そしてその歌人が生きた証として名を後世に遺したい、という思いまでにも心を配り、最大限に尊重しようとする定家の心遣い。
やはり、定家さまは神。(何回言うねん)
まさに行盛が定家に託した歌の内容通り、その身は壇ノ浦の水の底に沈んでも、彼の詠んだ歌は、数百年の時を越え、今も、これからも読み継がれていくのですね。
ちなみに、この行盛イメージ図の花は、『平家花揃』(※)の平行盛の項より、忘れ草です。
※『平家花揃』…室町時代に作られた平家の公達をそれぞれ花に例えた古典文学作品。
行盛が忘れ草だと……
ややこしいのですが、忘れ草(わすれぐさ)は、勿忘草(わすれなぐさ)ではなく、忘れる方の草です。
『花揃』が忘れ草でも、行盛のこと忘れないからね!!
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
なお、『新勅撰和歌集』には、行盛以外の平家の歌人も、本名で載っていますよ。
定家さま、ありがとう。
大宰府は安住の地となるのか
今回は和歌のお話がいっぱいでしたね。さすが雅な平家の公達。
(^^)
さて、平家は大宰府を拠点として再起を図るつもりでした。
けれども、既に後鳥羽天皇を擁立している京の朝廷側は、安徳天皇の内裏など認めるわけにはいきません。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
次回、豊後の知行国主藤原頼輔、その子頼経の命を受けた緒方惟義が、大宰府に攻めてくる?!
資盛と貞能のとった行動は…
資盛と貞能のとった行動は…
次回更新は、年末年始を挟んで1月中~下旬頃の予定です。
少し間が空いて申し訳ありません。
m(_ _)m
いつもお読みいただいて、ありがとうございます。
皆さま、よいお年をお迎えください。(^^)